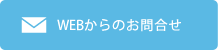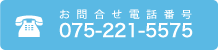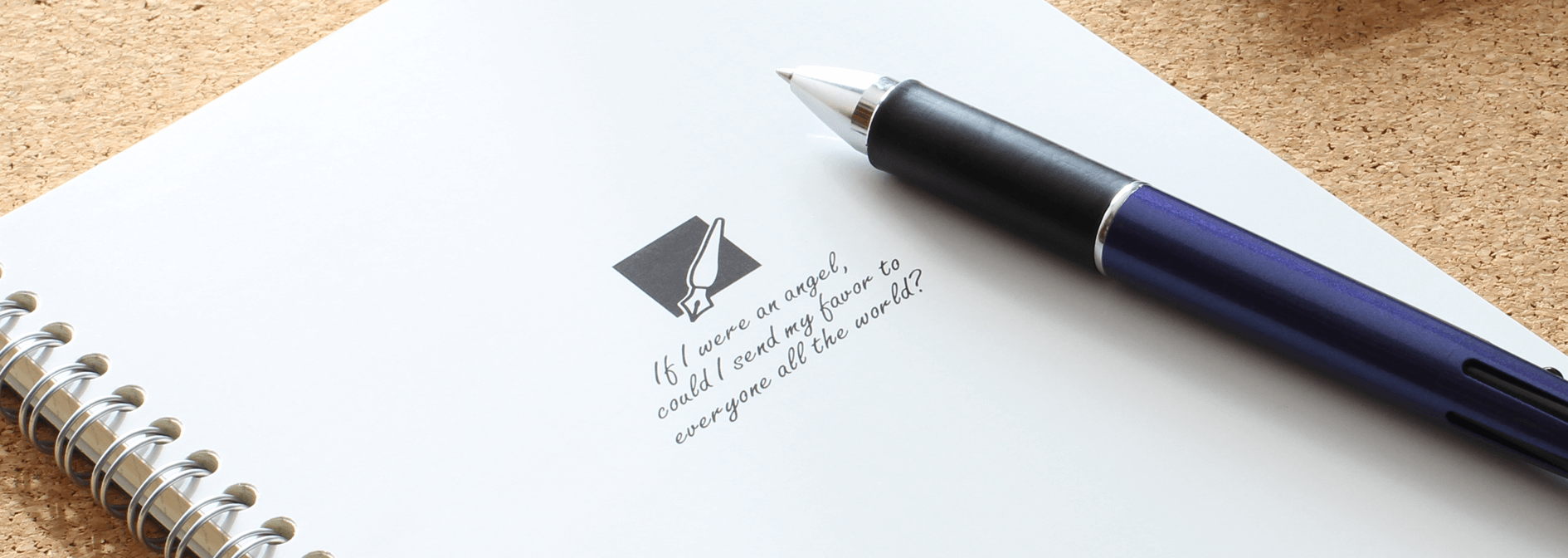ほんとうの憲法を学ぶ勉強会(修正)
11月4日から、当事務所にて少人数の勉強会を行いますので、
ご興味のある方はご連絡下さい!
zoom参加も可能となりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ほんとうの憲法を学ぶ勉強会
安達法律事務所
弁護士 安達悠司
これまでの法律的常識を取り払い、わが国の2000年以上にわたる歴史をふまえ、憲法とはいったい何なのかを一から考える勉強会です。
憲法は、我が国の基本法であり、本来はこれを学ぶことにより、国を尊び、祖先を敬い、国民の生活を安らかで豊かにするものであるべきです。
この勉強会は、憲法を学ぶことにより、心を養い、視野を広げ、叡智を身に付け、各々の人生を豊かにすることを理想として行います。
新進気鋭の政治家・学者・経営者必見です。一般の方や学生、初心者の方も大歓迎です。テーマは大きいですが、法律の常識にとらわれない、いつでも質問可、途中入退室自由、少人数のアットホームな場にしようと思います。
■日時■ 令和2年11月4日(水)午後6時30分~午後8時30分
■場所■ 安達法律事務所 京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木五丁目470番地
竹屋町法曹ビル2階(TEL 075-221-5575)
地下鉄烏丸線丸太町駅 徒歩3分 駐車場なし
■費用■ 1000円(税込) zoom視聴の場合は事前の振込をお願いします。
■定員■ 10名程度(予約順)+ zoom視聴の参加者
■内容■ ほんとうの憲法に関する勉強会 ①憲法と天皇
弁護士安達悠司の解説により、憲法における中心的存在である天皇について学びます。「天皇」とは何か、天皇の定義を調べてもほとんどの憲法の解説には書いてありません。なぜ最も中心的存在である天皇の定義の問題を多くの憲法学者が避けているのか?天皇の定義を調べることは我が国の憲法の重大な問題にたどりつきます。それは、、、。解説90分、質疑応答+意見交換
■申込■ 下記申込書をFAXしていただくか、電話・メール(adachi@adachi-kyoto.com)にてご連絡ください。残席あれば当日参加も可能です。
☆zoom参加の場合☆ 必ず前日までにメールにてご連絡ください。振込先をご連絡しますので、お振込後に配信方法をメールでご連絡します。
■次回以降の日程■
11月12日(木)午後6時30分~午後8時30分 ②憲法の基本原理
11月18日(水)午後6時30分~午後8時30分 ③十七条憲法
12月 2日(水)午後6時30分~午後8時30分 ④憲法と国防
12月10日(木)午後6時30分~午後8時30分 ⑤あるべき憲法とは
(各回は別個の内容であり、単発での参加も可能です。)
検察庁法改正に関する日弁連会長声明に対する私見
R020511日弁連会長声明に対する私見_R020512
検察庁法改正に関する日弁連会長声明に対する私見
1 日弁連会長声明の要旨
日弁連は、令和2年5月11日付の「改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明」において、次のとおり述べ、検察庁法の改正に反対している。
「当連合会は、検察官の65歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが、内閣ないし法務大臣の裁量により役職延長や勤務延長が行われることにより、不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。『準司法官』である検察官の政治的中立性が脅かされれば、憲法の基本原則である三権分立を揺るがすおそれさえあり、到底看過できない。少なくとも当該法案部分は削除されるべきである。」
要するに、日弁連は、内閣ないし法務大臣の「裁量」によって定年後の役職延長や勤務延長がなされる「危惧」を理由に、制度自体に反対している。
2 検察官に対し、内閣及び法務大臣の人事権等が既に存在すること
検察官は、捜査及び起訴等の強大な権限を有し司法的役割を果たしているが、裁判所のような司法機関そのものではなく、あくまで法務省に属する行政機関である。日弁連も検察官を「準司法官」と述べている。
現に、現行の検察庁法は、検察官が法務大臣の指揮監督下にあり、法務大臣が検察官の任命、叙級、検察官適格審査会に対する請求、罷免、剰員検察官の処遇その他の人事権を有することを定めている。ただし、検事総長・次席検事・検事長の任免権限は、内閣に帰属する。
【内閣の検察官に対する権限】
・検事総長、次長検事及び各検事長の任免(15条1項)
【法務大臣の検察官に対する権限】
(任命)
・検事長、検事及び副検事の任命(16条1項)
・一級及び二級検察官の叙級(18条及び19条)
(罷免)
・検察官適格審査会に対する請求(23条2項2号)
・検察官適格審査会の議決を相当と認める場合、検事総長、次長検事及び各検事長に対する罷免の勧告または検事長、検事及び副検事の罷免(23条3項)
(その他人事権)
・高等検察庁又は地方検察庁の支部勤務の命令(17条)
・検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となった場合、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせる(24条)
(指揮監督権)
・検察官に対する一般の指揮監督(13条2項)
・個々の事件の取調又は処分に関し、検事総長に対する指揮監督(13条2項)
・検察庁の事務章程の制定(32条)
したがって、検察官の人事に関する終局的権限は、内閣及び法務大臣に属しており、定年後の役職延長・勤務延長に関しても、この制度を設けるとすれば、その終局的権限は当然に内閣及び法務大臣に帰属すべき問題である。
3 定年後の役職延長・勤務延長の制度の必要性
他の国家公務員一般については、定年後の役職延長・勤務延長の制度が既に存在する(国家公務員法81条の3)。
そこで問題は、①検察官について、定年後の役職延長・勤務延長の制度が必要あるか、②検察官について定年後の役職延長・勤務延長の制度を設ける場合に、誰がどのように判断する制度設計にすべきか、である。
①の検察官の定年後の役職延長・勤務延長制度の必要性について、まずは、必要性に関する具体的な議論がなされるべきであるが、日弁連の会長声明は、具体的な理由を述べることなく否定している。検察官は捜査・起訴権限を有し、事案の終結まで年単位の期間を要する事案が多く、特に重大事件において長期化する例もしばしば見受けられ、特段の事情がある場合に役職延長や勤務延長制度を設けておくべき必要性自体を否定する論拠は乏しいと思われる。
②の制度設計についても、日弁連の会長声明は何も述べていない。任命・叙級・剰員の待遇等の人事権限が基本的に法務大臣に帰属することを踏まえると、法務大臣に権限を帰属させることが合理的である。また、改正案では法務大臣が準則を作成し、これを踏まえて延長の判断を行うこととなっているが、この制度設計自体も直ちに不合理とは言えない。
4 日弁連の「危惧」は抽象的であり、運用の問題に過ぎないこと
日弁連は、上記①②について具体的な理由を指摘することなく、抽象的一般的に、役職延長・勤務延長制度ができた場合に、内閣や法務大臣の「裁量」によって検察官の独立性侵害ひいては三権分立違反となることを危惧し、制度創設そのものに反対している。
しかし、検察官は法務省の特別機関であり、法務大臣は既に検察官に対する任命・叙級・検察官適格審査会に対する請求・罷免等の人事権・指揮監督権限(内閣は検事総長等の任免権限)を有しており、検察官に対し、内閣や法務大臣の「裁量」を前提とする制度が現に存在して機能している。今回、定年後の1年間・最長3年間の役職延長・勤務延長について、内閣や法務大臣の「裁量」の存在だけを理由に、制度そのものに反対するのは具体的論拠が乏しい。
また、日弁連が指摘する「検察官の独立性侵害」「三権分立違反」は、日弁連が述べているとおり、あくまで「危惧」にすぎず、法改正後の運用や個々の事案における裁量の問題であり、法改正によって発生する具体的な弊害や影響とは区別しなければならない。ましてや、今回の改正案では法務大臣が準則を作成し、準則に基づく延長の判断が行われるものであり、尚更恣意的な裁量行使がされるおそれは低い。
運用についての抽象的な「危惧」は、いかなる法律制定や法改正に対しても言えることであり、法改正そのものに反対するほどの強い論拠ではない。
運用についての抽象的な「危惧」だけを理由に、必要性や制度設計に関する議論を一切することなく、改正自体に反対するのは拙速であり、論理に飛躍がある。
5 今回の会長声明が政治的公平性・中立性を損なうおそれ
日弁連は、全国の弁護士会及び弁護士が強制的に登録している団体であり、特定の法律案に対して意見を述べるのであれば、法律専門家として、法案に対する法律上の問題点を具体的かつ客観的に検討・指摘すべきであって、いやしくも政治的公平性を損なうことのないように配慮しなければならない。
検察庁法改正案について、運用上の懸念を示すにとどまらず、改正そのものについて明確な反対意見を述べるならば、相応の法律上の根拠を示すべきであるが、今回の会長声明においてそれがなされているとは言えない。
今回のような拙速かつ論拠に乏しい会長声明の濫発は、日弁連の会長声明が、政治的・恣意的になされているのではないかとの疑念を抱きかねず、日弁連自体の政治的公平性・中立性を損なうおそれが高い。
以上より、頭書の日弁連会長声明に反対する。
以上
令和2年5月12日
弁護士 安達悠司
R020511日弁連会長声明に対する私見_R020512
通常どおり営業中です。
安達法律事務所は、通常どおり営業中です(土日祝休み。ただし事前予約による相談等は可能)。
法律事務所及び弁護士会は、法律を通じた司法秩序の維持という公共的な役割を担っております。
中でも、債権回収、訴訟提起、差押え等への対応、不動産紛争、労働紛争、民事保全、民事執行、破産、
民事再生・個人再生、任意整理、離婚、遺言、相続、家事審判前保全、後見事務の遂行、刑事弁護、
少年付添、被害者支援その他数多くの緊急性の高い案件に備えることが必要ですが、その窓口はすべて
法律相談から始まり、また受任した業務も遂行し続ける必要があることから、法律事務所の業務は、
生活の維持に必要不可欠といえます。
したがって、本年4月7日に緊急事態宣言が発令された現在も、通常どおり、営業を行っております。
感染症予防にも努めた上、通常の法律相談、出張相談等を行うほか、面識のあるお客様については
電話・WEB会議等による相談も受けられる場合がありますので、お問い合わせください。
11月28日(木)18:30~ アットホームな勉強会のお知らせ
皆様
このたび、納谷社会保険労務士事務所と共同して、11月28日に
少人数の勉強会を開催いたします。
経営者の方にとって必要不可欠な労務管理に関する問題を取り扱います!
初めての試みですが、お気軽にどうぞ!
以下案内です。
—————————————————————————————————-
※11/28(木)開催!!
弁護士・社労士によるアットホームな勉強会
~働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマにわかりやすく解説~
今回、弁護士と社会保険労務士が共同して、働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマに、下記の要領で勉強会を開催することとしました。
経営者の方、会社役員の方、会社員の方、団体・法人の方、士業の方、学生の方、初めての方でも基礎から実務まで分かりやすく解説いたします。
アットホームな勉強会ですので、現行のご不安やご質問もして頂けます。
まずは、一度お越し下さい!!
◆日時◆ 令和元年11月28日(木)午後6時30分~午後8時30分
◆場所◆ ウイングス京都 会議室11
〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 番地
◆解説内容◆
①「働き方改革に中小企業はどう向き合うか?」
―年次有給休暇取得と時間外労働のための対策を基礎から実務まで解説―
解説者:納谷社会保険労務士事務所 社会保険労務士 納谷朋美
②「残業代をめぐる裁判と経営者の心得」
―労働時間管理のあり方や裁判等への対応を解説―
解説者:安達法律事務所 弁護士 安達悠司
◆会費◆ 2000円(税込)
◆定員◆ 20名(先着順)
◆申込方法◆
※当日参加も可能ですが、できる限りお早めに申込みをお願いします。
事前にお申込みされる方は、安達法律事務所まで、お名前、御社名・団体名、人数、電話番号をお知らせください。
申込方法① adachi@adachi-kyoto.comまで
※メールの題名に「勉強会参加希望」とお書きください。
申込方法② 安達法律事務所までお電話ください(075-221-5575)
※平日9:30-17:30の間にお願い致します
申込方法③ Facebookページで「参加予定」としてください。
https://www.facebook.com/events/437014160322195/
以上
泉本宅朗弁護士退所のお知らせ
さて、このたび、本年12月末日をもって、当事務所で勤務していた泉本宅朗弁護士が大阪市内で独立開業のため退所することとなりました。
もともと、交通事故の事件を中心に大阪での5年間の経験を積んでおり、当事務所には1年間という短い期間でしたが、大変温厚・誠実な人柄で、交通事故だけでない様々な事件について、丁寧で真面目に相談・事件処理に取り組まれました。
当事務所での様々な事件の経験を通じ、また、大阪から相談される依頼も多くあり、独立開業に踏み切る決意に至ったとのことで、弁護士として業務の幅を広げ、ますますこれからの活躍が期待されます。
今後とも皆様の変わらぬ支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
以下、泉本弁護士の挨拶文を掲載します。
京都弁護士会に入会させていただいて1年足らず、短い期間でしたが、この度安達悠司弁護士のお許しのもと、慣れ親しんだ大阪の地に再び戻り、来年1月より開業の運びとなりました。
幅広い分野についての経験をさせていただくことで、独立に向けての自信もつきました。京都に移った後も大阪方面からの相談が少なくないため、独立開業を決意した次第ですが、この1年で学ばせていただいたことを少しでも活かすことで、お世話になりました京都の皆様方へのご恩返しをさせていただけるよう精進を続けたいと思います。
京都弁護士会の諸先生方、事務局の方々、本当に有難うございました。皆様方の益々のご壮健とご発展をお祈りしつつ、退会の挨拶とさせていただきます。
平成29年12月吉日
〒542‐0012
大阪市中央区谷町六丁目6‐7 第五松屋ビル611号
星のしるべ法律事務所
弁護士 泉 本 宅 朗