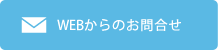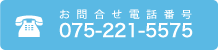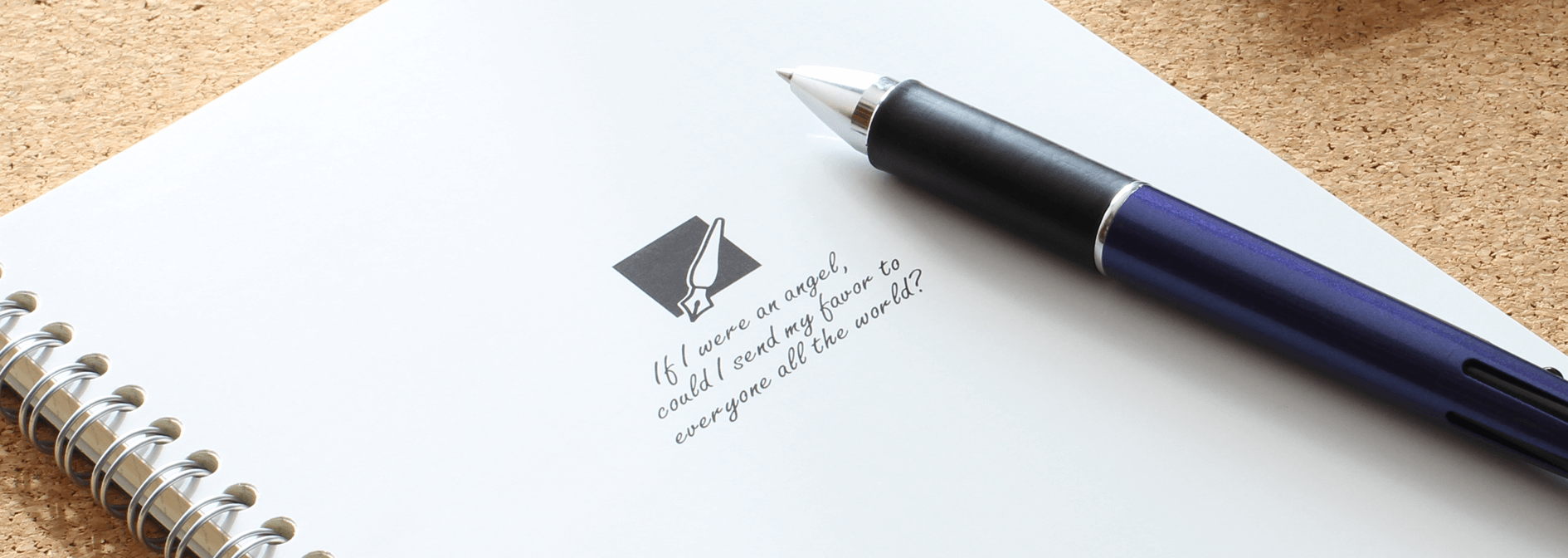病院・福祉施設における画一的面会禁止は違法
日本弁護士連合会(日弁連)は、令和3年4月16日、「コロナ禍における社会福祉施設・医療施設での面会機会の確保を求める意見書」を発表した。
日弁連は、病院・福祉施設などに入居する高齢者・障がい者にとって,面会の重要性を次のように指摘する。
「面会は健康面・身体面での意義に限らず,人とのコミュニケーションを取り,社会とのつながりを感じることで得られる幸福感を充足させるといった精神面での意義をも有している。人と面会して,コミュニケーションを取る権利は,人格的価値,関係性構築にかかる価値につながるものであり,社会福祉施設や医療施設に入所・入院している高齢者・障がい者にとって,面会をすることは人格的生存に不可欠であるため,憲法第13条の規定する幸福追求権として保障されるべき人権である。また,国際人権自由権規約は,何人も,その私生活,家族,住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉されず,かかる干渉に対する法律の保護を受ける権利を有するとしている(同規約第17条第1項)。」
このように、面会の権利は、憲法上保障され、国際人権自由権規約でも保障されているのみならず、「人格的生存に不可欠」とまで明記される非常に重要なものである。
日弁連は、こうした入居者の面会を長期間制限することにより、次のような悪影響が生じると指摘する。
「長期間にわたり家族等の身近な人との面会が制限されることにより生じる本人への影響として,高齢者についての調査研究の結果によれば,ADL(IADL)3の低下,認知機能の低下,行動心理症状の出現・悪化,身体疾患の悪化,身体活動量の低下,意欲の低下又は興味・関心・意欲の低下が生じ,健康被害や死亡に至るリスクが高まること(いわゆるフレイル化)が明らかになっている。」
なお、ADLとは,「日常生活動作」のことであり,起床,食事,着替え,入浴等の日常の基本的な動作を指す。IADLとは,「手段的日常生活動作」のことであり,ADLに比べて,より高度な運動や記憶力を要する動作を指す。(例えば,買い物や電話の対応等。)また、調査研究として、広島大学「【研修成果】新型コロナウイルス感染症の拡大により,認知症の人の症状悪化と家族の介護負担増の実態が明らかに~全国948施設・介護支援専門員751人のオンライン調査結果~」(https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/59484)が引用されている。
そして、日弁連は、こうした面会の重要性に鑑み、「必要な物的・人的体制整備を行い,地域の感染状況に応じて,感染防止と面会機会の確保のバランスの取れた対応を行うように努め,一律の面会禁止を行うなど画一的な対応を講じることのないようにすること。」を提言している。
また、日弁連は、特に、「面会禁止措置を講じることがやむを得ない場合であっても,精神科病院における退院・処遇改善請求手続のための面会,②看取り期の面会,③喫緊の懸案事項があり本人の意思を確認することが不可欠な場合や意思決定支援など,権利擁護の観点からの面会等は認められるべきである。」と述べている。
こうした提言から、(1)画一的な面会禁止は違法である、(2)仮に、何らかの面会禁止措置を講ずる場合であっても、①精神科の退院・処遇改善のための面会、②看取り期の面会、③権利擁護の観点からの面会等を禁止するのは違法である、と考えられる。
「新型コロナウイルス感染症」に関し、連日の加熱した報道や宣伝により、従来の他の感染症への対応に比べ、国民が過剰反応しているケースが見受けられ、その結果、本来認められている重要な人権が無視され、蹂躙される場面が少なくない。そうした中でも、日弁連が、社会正義と基本的人権の擁護のために、こうした面会の権利を守るという意見書を出している点は注目に値するものである。
日本弁護士連合会:コロナ禍における社会福祉施設・医療施設での面会機会の確保を求める意見書 (nichibenren.or.jp)
追加接種や12歳未満の接種について
新型コロナウイルス感染症対策と称して、治験中の海外製「ワクチン」の3回目の追加接種を政府や自治体が勧める動きがあります。
さらには、12歳未満の小学生や幼児をもターゲットにして、同じく治験中の海外製「ワクチン」を接種させようとする政府や製薬会社の動きが活発化しております。
しかしながら、これらの3回目の追加接種や子どもへの接種について、多くの死亡例が見受けられるほか、接種の危険性を指摘する見解が強く、また、中長期的な安全性が十分に明らかにされておらず、現時点の知見では、接種は控えた方が無難です。
1 村上康文博士(東京理科大学名誉教授)のForbes Japan掲載記事
Forbes JAPAN 編集部 FORBES JAPAN 世界38カ国、800万人が愛読する経済誌の日本版
テクノロジー 2021/09/10 13:00 「すべての新型コロナ変異株に対応?「口内に噴霧」の非mRNA型予防薬、商品化へ」 https://forbesjapan.com/articles/detail/43274/
2021/09/11 16:15 「【寄稿】パンデミック収束に、ワクチンは重要な役割を担う|東京理科大学名誉教授 村上康文」 https://forbesjapan.com/articles/detail/43300
これらの記事では、
●「同一の抗原で繰り返し免疫化を行った場合、動物実験では5回目から死亡する例が増加。7〜8回繰り返すと半分近くが死亡するという動物での研究結果もある」とも東京理科大学名誉教授、村上康文氏は話す。
●一方で3回目以降の「ブースター接種」についてですが、とくに慎重に進めていくべきであると考える研究者は、私を含め、少なくありません。
などと、追加接種を慎重にすべきとの意見が記載されています。
2 薬のチェック編集委員会「薬のチェック」掲載記事
また、薬のチェック編集委員会「薬のチェック」JAN. 2022/Vol.22 No.99、22頁や、
https://npojip.org/chk_tip/No99-f06.pdf
薬のチェック編集委員会「薬のチェック」 SEP. 2021/Vol.21 No.97、118頁
https://npojip.org/chk_tip/No97-f06.pdf
では、未成年者に対するワクチン接種後の死亡例や、接種の危険性が記載されています。
3 北海道有志医師の会意見表明
さらに、北海道の有志の医師の意見表明では、ワクチン接種中止や接種による免疫力低下の懸念が指摘しされています。
ひとまず最終版です(リンクあり) | おおきな木ホームクリニック (o-kinaki.org)
児童に関しては、現在、新型コロナウイルス感染症が報告されてから2年近くになますが、我が国では、小児は感染しても多くが無症状から軽症で経過しており、15歳未満の小児の死亡例はゼロで、重症例や MIS-C もきわめてまれであると言われています。これは、日本感染症学会「COVID-19 ワクチンに関する提言(第4版)」24頁にそのように記載されています。
皆様も、このような情報も心に留めていただき、追加接種や12歳未満の接種について、くれぐれも慎重にご判断くださいますようお願い申し上げます。
ワクチン接種の強制や差別は法律で禁止されています!
ワクチンを接種する・しないによる差別は法律で禁止されています!
厚生労働省は「職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、皆さまにお願いしています。」と明確に差別禁止を要請しています。
ワクチン接種の強制・接種しないことに対する差別などに困られた場合は、お近くの弁護士会・法律事務所まで相談しましょう!
以下厚生労働省ウェブサイトの引用です。
厚生労働省ウェブサイト 新型コロナワクチンQ&A「新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。」
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0053.html
Q 新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。
A 新型コロナワクチンは、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
新型コロナワクチンについては、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。
しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、皆さまにお願いしています。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。なお、職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちらを、人権相談に関する窓口はこちらをご覧ください。
(参考資料)
ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)
経済団体等への協力依頼(厚生労働省)
年末年始の営業について
いつもご厚情を賜りありがとうございます。
安達法律事務所は、令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)までは年末年始の休業期間となります。
令和4年1月4日(火)午前9時30分より営業しています。
コロナ・マスク・ワクチン差別に関する無料相談について
【コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種等による差別に関する無料相談について】
1.コロナ感染、マスクの不着用、ワクチンの非接種による不合理な差別や不利益取扱いが許されないこと
新型コロナウイルス感染症のPCR検査が陽性であるからといって、症状がない場合は特に、他人に感染させる状態にあるとは限りません。
また、新型コロナウイルス感染症(武漢肺炎、covid-19)に感染して発症した場合であっても、治療や感染防止に伴う合理的な根拠のある最小限度の制約を除き、不合理な差別や不利益取扱いが許されないことは言うまでもありません。
また、国民にはマスクの着用を強制されない自由があります。
マスクは、本来、医療関係者など特殊な場合を除いて、体調不良の場合に、本人の健康状態を勘案し、自主的に着用するかどうかを判断するものです。
マスクによる感染予防効果や、マスクによる感染拡大防止効果は未だ明確ではありません。
他方で、マスク着用は、酸素不足による生命身体への危険、児童の情操への影響や免疫力の低下、コミュニケーションの不活化等の着用による弊害も指摘されています。
したがって、国民全員のマスク着用が最善であるとの考え方は、いまだ一個の仮説にすぎず、絶対的なものとして他人に押し付けるべきものではありません。
またマスク着用により現に健康や心身への影響が発生し発生するおそれがある者に対し、合理的な根拠なくマスクの着用を求めたり、マスクの不着用により不合理な差別や不利益取扱いをすることは現に慎まなければなりません。
また、国民には、ワクチンの接種を強制されない自由があります。
特に、今回のワクチンは海外製で、承認までの期間も非常に短く、日本人に対する予防効果や長期的な安全性が未確認であることや、予防の対象となる新型コロナウイルス感染症の病毒性や感染力が明確でないことから、ワクチン接種を望まない考え方には相応の合理性があります。
ワクチンを接種しないことを理由に、職場、官公庁、取引先、学校、医療機関等で不利益的な扱いをなすことは厳に慎まなければなりません。
特に、国民全員に今回のワクチンを接種することが、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を予防する目的に照らして最善であるかどうかは、必ずしも明確ではありません。
国民全員に今回のワクチンを接種した場合も、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を防止することができず、かえって副作用による死亡者の増加や、変異株の発生促進による流行の拡大をもたらすおそれがあるとの指摘もあります。
したがって、現時点では、国民全員のワクチン接種が最善であるとの考え方は、一個の仮説にすぎず、逆の作用をもたらすおそれも十分にあるため、これを絶対的であるとして他人に押し付けることは好ましくありません。
このように、コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種による不合理な差別や不利益取扱いは許されないものです。
日本国憲法は公共の福祉に反しない限度で個人の自由を認めるとともに、不合理な差別を禁止しています。この憲法の規定は、法律や命令に優先するものです。
また、新型インフルエンザ特措法(新型コロナに適用)5条は、個人の権利の制限は感染症対策にとって必要最小限度のものでなければならないと定めています。つまり、感染症対策として何らかの行為を、法律や命令で強制するには、その行為が必要であることと、最小限度の制限であることが証明されなければなりません。
さらに、13条2項は、コロナ感染者やその家族や組織に対する差別が禁止されることを確認し、国や自治体がその広報をするべきことを義務付けています。
このように、法律上も、個人の生命身体の自由を認めるとともに、感染者に対する不合理な差別や不利益取扱いが禁止されているのです。
2.和らぎ、謹み、敬いの考え方をもって話し合うこと
コロナ、マスク、ワクチンをめぐる考え方は人によって違います。また何が正しいかも未だ明確とはいえません。
聖徳太子の十七条憲法では、互いに考え方が違うことを前提として、どのように行動すべきかが書かれています。
まず、和らいだ雰囲気、和やかな空気をつくりだすことです。これは上司の役割とされています。
和らいだ空気のもとで、なぜそう考えるかを伝え合い、話し合えば、お互いに思ってもみなかった情報を知ったり、意外な体験談を聞くことができるものです。
また、集団の中心となる存在、特に目上の人や上司に対して、ことばや行動に謹みをもって接することも大切なことです。
さらに、目上、目下に限らず、互いに敬いの行動をもって接することです。具体的には挨拶、お辞儀、感謝のことばなどです。
真実が明確でない中で、対応していくわけですから、互いに謙虚に接し合うことが求められます。
国民に、個別の事情に配慮せず、マスクやワクチンを事実上強制させるような考え方は、この謙虚さを失っています。
3.相談について
コロナ感染、マスク着用・不着用、ワクチン接種・非接種に伴う不合理な差別や不利益取扱いは、法律相談になることが多いと考えられます。
このような相談は各地の法律事務所や弁護士会で受け付けていると思います。
安達法律事務所では、上記問題(コロナ感染、マスク着用、ワクチン接種等)について、当面の間、無料相談を行っておりますので、よろしければご連絡ください。
ご参考
日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
基本的人権の尊重
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
知識の普及等
第十三条
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為