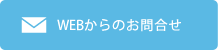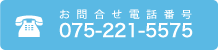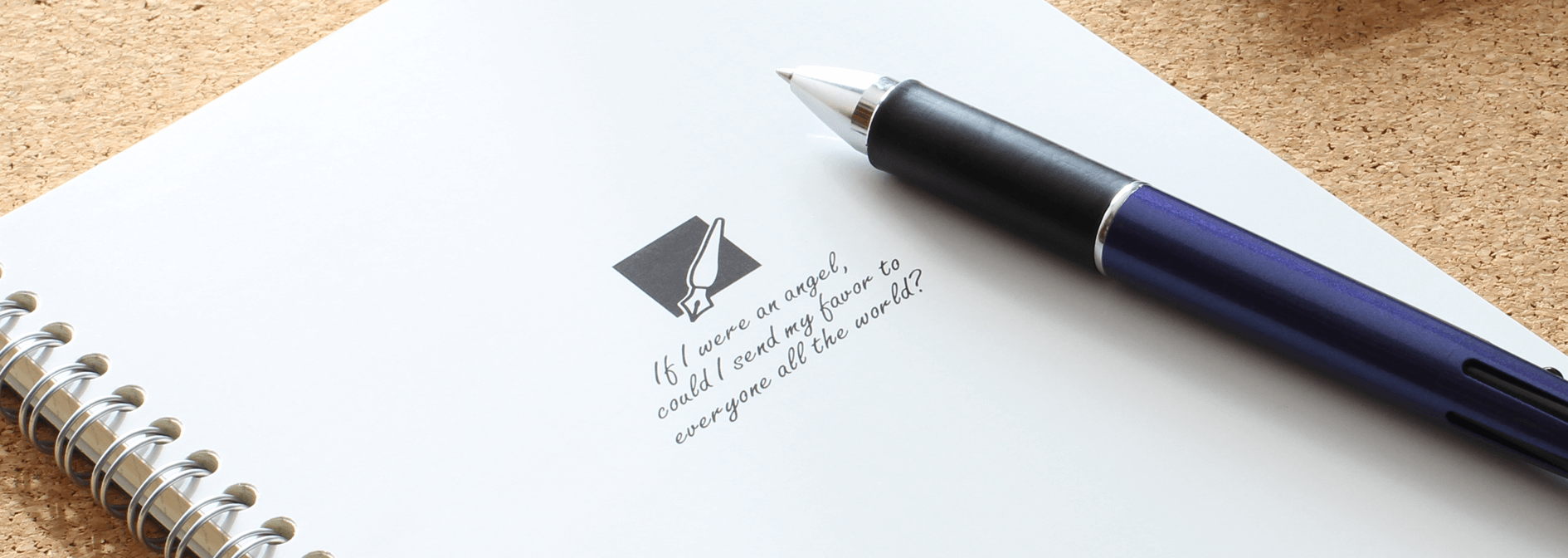新型コロナワクチンをどうみるか
新型コロナワクチンに関し、
昨年12月28日に、一般社団法人日本感染症学会が提言を出している。
COVID-19ワクチンに関する提言(第1版)
https://www.kansensho.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=43
この提言によれば、欧米の製薬会社の新型コロナワクチンについて、次の問題点が指摘されている。
1 従来のワクチンにくらべて、副作用が重大
疼痛の中でも、ファイザーのワクチンでは、1 回目接種後の約 30%、2 回目接種後の約 15%に、日常生活に支障が出る中等度以上の疼痛が報告されています。疼痛の 70~80%という頻度は、成人における不活化インフルエンザワクチン接種時の頻度 10~22%に比べてはるかに高く、比較的接種部位の疼痛が強いとされている 23 価肺炎球菌ワクチン(PPSV23)の 58.3%、13 価肺炎球菌ワクチン(PCV13)の 68.2%と比べて同等もしくはそれ以上です。アストラゼネカのウイルスベクターワクチンでも若年者群で疼痛の頻度が高くなっています。
mRNA ワクチンでは、さらに全身反応の有害事象が高頻度にみられています。とくに、 倦怠感、頭痛、寒気、嘔気・嘔吐、筋肉痛などの頻度が高くなっていますが、これらの症状は対照群でもある程度みられていることに注意が必要です。
発熱(38℃以上)は 1 回目では少ないですが、2 回目の接種後に 10~17%みられています。発熱は対照群ではほとんどみられていませんので、ワクチンによる副反応の可能性が高いと思われます。とくに高齢者よりも若年群で頻度が高い傾向があります。不活化インフルエンザワクチン、PPSV23、PCV13 の発熱の頻度は、それぞれ 1~2%、1.6%、4.2%で すので、mRNA ワクチンでは注意が必要です。
2 アジア人、高齢者、基礎疾患がある者のデータが乏しい
これらの臨床試験の被接種者は白色人種がほとんどで、アジア系の割合が少ないため、人種による副反応の頻度の違いがあることを前提に、国内での臨床試験の安全性の確認が欠かせません。さらに、これらの臨床試験における 75 歳以上の割合は、ファイザー0.4%、モデルナ 0.5%であり、アストラゼネカの臨床試験でも 70 歳以上が 6.8%にすぎず、超高齢者への 接種の安全性も十分確認されているとは言えません。またさまざまな基礎疾患をもつ方も 被接種者に含まれているとは言え、その数は十分ではありませんので、今後さらに基礎疾患ごとの安全性を検討する必要があります。
3 ADEなどについて、長期的な安全性が検証されていない
数年にわたる長期的な有害事象の観察が重要です。 また、ワクチンによる直接的な副反応とは言えませんが、接種を受けた人が標的とした病 原体による病気を発症した場合に、接種を受けていない人よりも症状が増悪するワクチン関連疾患増悪(vaccine-associated enhanced disease, VAED)という現象にも注意が必要です。過去には、RSウイルスワクチンや不活化麻疹ワクチン導入時に実際にみられています。またデング熱ワクチンでは、ワクチンによって誘導された抗体によって感染が増強する抗体依存性増強(antibody-dependent enhancement, ADE)という現象の可能性が疑われ、接種が中止されました。COVID-19 と同じコロナウイルスが原因である SARS(重症急性呼吸器症候群)や MERS(中東呼吸器症候群)のワクチンの動物実験でも、一部に VAED を示す結果がみられています。COVID-19ワクチンの動物実験や臨床試験では、これまでのところ VAED を示唆する証拠は報告されていませんが、将来的に注意深い観察が必要です。
そのうえで、有効性と安全性が検証されていないワクチンについて努力義務が適用されない
ことも指摘されている。
このようにみると、新型コロナワクチンの接種により、
・疼痛、倦怠感、頭痛などの副作用が非常に高い頻度で起きる
・38度以上の発熱が起きる割合も高い そうすると、高齢者や基礎疾患者への接種はむしろ危険ではないか
・長期的な有害事象の安全性が検証されていない。
という危険性が残存していることがわかる。
ワクチンによる薬害はこれまで多くの例で生じており、
上記提言をみても、拙速な接種がむしろ危険であると感じられる。
2/9 弁護士・社労士による勉強会(第6回)のお知らせー採用の実務ー
社会保険労務士の納谷先生と共同で開催する勉強会のご案内です。
皆様ふるってご参加ください。
日本を元気にする!経営者のための弁護士・社労士による勉強会のご案内
~緊急!新型コロナ対策情報交換会(Zoom参加型)~
弁護士と社会保険労務士による勉強会第6弾を開催することと致しました。今回のテーマは、事業者の新型コロナウイルス対策に関する情報交換です。昨今の情勢に鑑み、WEB会議システム(Zoom)を取り入れての初めての試みとなります。経営者の方、会社役員の方、会社員の方、団体・法人の方、士業の方、学生の方、初めての方でも大歓迎です。
◆日時◆ 令和3年2月9日(火)午後6時30分~午後8時30分
◆場所◆ ハートピア京都(京都府立総合社会福祉会館)4階 第4会議室
〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地 ※今回は、開催場所が変わりますのでご注意下さい。
◆内容◆ 法律家からみた「採用」のポイントとその実務
1 弁護士・社労士からの発表(90分)
① 弁護士からみた「採用」にまつわる注意すべきポイント (安達悠司弁護士)
② 社労士からみた「採用」にまつわるポイントと実務 (納谷朋美社会保険労務士)
2 参加者からの質疑応答・ディスカッション(20分)
◆会費◆ 2000円(税込)
◆定員◆ 20名(先着順)
◆申込方法◆
【直接参加の方】当日参加も可能ですが、できる限りお早めに申込みをお願いします。
申込方法は、「参加予定」と表明していただくか、安達法律事務所までご連絡下さい。
(電話075-221-5575、メールadachi@adachi-kyoto.com)。
【zoom参加の方】前日までにメール等による申込みとお振込が必要です。参加のためのURLと振込先を送付させて頂きますので、必ずメールアドレスをご記入下さい。
◆zoomの場合の参加方法◆
主催者からZoom参加のためのURLを送信いたします。
各自でインターネット接続環境とZoomアプリを用意していただき、WEB会議システムによる参加が原則となります。
また、Zoomアプリにより参加していただく際は、参加者皆様の表情などが分かるよう、映像と音声をオンにした状態で参加してくださいますようお願いいたします。
十七条の憲法について(全文解説PDF付き)
末尾に、弁護士安達悠司による十七条憲法の解説全文をPDFファイルでダウンロードできます。
聖徳太子の「十七条の憲法」をご存じでしょうか。今から1400年以上前(推古天皇12年・西暦604年)に聖徳太子が作った我が国最古の成文憲法と言われ、その全文が「日本書紀」に掲載されています。有名な「和を以(もっ)て貴しと為(な)し」から始まり、17カ条にわたり、官吏に対する職務のための心得を説くものです。
聖徳太子は天皇を中心とする我が国古来の教えを基本としながらも、海外から伝来した仏教や儒教も取り入れて、当時の最先端の教えの体系を確立しました。なぜ私がこれに着目するかというと、今でも公務や仕事に生かせる内容がたくさん含まれているからです。
たとえば、第1条は「和を以て貴しと為し」から始まります。「和」は「やわらぎ」と読みます。音読みではなく、訓読みで読むのが我が国古来の読み方だったのです。意味も、単に協力するという意味だけでなく、仕事をする上で、「やわらいだ雰囲気を大切にしましょう」という教えを説くものと考えられます。
世の中には様々な考え方の人がいますから、ギスギスした空気で議論すると、角がたってしまいます。しかし、「上司が率先してやわらいだ空気を作り出して話し合えば、部下と考えが通じ合い、心を一つにして物事に取り組むことができますよ」というのが第1条の教えです。
私が仕事をする上でも、やわらいだ雰囲気のもとで交渉や調停を行えば、よくまとまります。裁判官の中にはそうした空気をかもし出すのが得意な方が大勢いらっしゃいます。
また、第9条では「信(まこと)は是(こ)れ義の本なり」と述べられています。正直でうそをつかないことを、当時の日本人も美徳としていたことが分かります。現代の民法にも、信義に反するような行動や契約は許されないという「信義誠実の原則」が定められています。
「十七条の憲法」の精神は今に至るまで、我が国の法文化の根底に息づいています。仕事をする上でも、憲法を考える上でも、先人が作り上げた「十七条の憲法」の精神を取り入れてみてはいかがでしょうか。
弁護士安達悠司による十七条憲法の解説全文をPDFファイルでダウンロードはこちら
訓読みで読む職場の人間学としての十七条憲法(弁護士安達悠司)
1/14ほんとうの憲法を学ぶ勉強会のお知らせ
ほんとうの憲法を学ぶ勉強会の総集編のご案内です。
☆ほんとうの憲法を学ぶ勉強会☆zoom参加も可能!
これまでの法律的常識を取り払い、わが国の2000年以上にわたる歴史をふまえ、憲法とはいったい何なのかを一から考える勉強会です。
憲法は、我が国の基本法であり、本来はこれを学ぶことにより、国を尊び、祖先を敬い、国民の生活を安らかで豊かにするものであるべきです。
この勉強会は、憲法を学ぶことにより、心を養い、視野を広げ、叡智を身に付け、各々の人生を豊かにすることを理想として行います。
新進気鋭の政治家・学者・経営者必見です。一般の方や学生、初心者の方も大歓迎です。テーマは大きいですが、法律の常識にとらわれず、いつでも質問可、途中入退室自由、少人数のアットホームな場にしようと思います。
zoom視聴のみによる参加も可能です!この場合は前日までに申込をお願い致します。
■日時■ 令和3年1月14日(木)午後6時30分~午後8時30分
■場所■ 安達法律事務所
京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木五丁目470番地 竹屋町法曹ビル2階(TEL 075-221-5575)
地下鉄烏丸線丸太町駅 徒歩3分
■費用■ 1000円(税込)
■定員■ 20名程度(zoom参加者) 会場は10名まで(予約順)
■内容■ ほんとうの憲法に関する勉強会 総集編
弁護士安達悠司の解説により、ほんとうの憲法について学びます。第1回から第5回までの勉強会の総集編です。2000年以上存続している世界最長の天皇を戴くわが国は、統治の理念や仕組みとしても、非常に優れたものを有しています。この2000年にわたる統治の在り方を通覧するとき、そこに何らかの法則があるのに気づきます。2000年以上変わらぬ統治の根本法則、それがほんとうの憲法です。我が国の在り方は、詔(みことのり)、十七条憲法、律令格式、近代憲法にとどまらず、三種の神器、数々の教えや歌などによって表現されてきました。我が国に今も生きている、ほんとうの憲法とは何でしょうか。90分、質疑応答+意見交換
■申込■
☆直接参加の場合☆
このイベントに参加予定と表明していただくか、または電話・メール(adachi@adachi-kyoto.com)にて個別にご連絡ください。残席あれば当日参加も可能です。
☆zoom参加の場合☆
個別にメールにてご連絡ください。振込先をご連絡しますので、お振込後に配信方法をメールでお知らせします。
■次回以降の日程■
未定
11/12(木)ほんとうの憲法を学ぶ勉強会(第2回)のご案内
ほんとうの憲法を学ぶ勉強会(第2回)のご案内
安達法律事務所 弁護士 安達悠司
これまでの法律的常識を取り払い、わが国の2000年以上にわたる歴史をふまえ、憲法とはいったい何なのかを一から考える勉強会です。憲法は、我が国の基本法であり、本来はこれを学ぶことにより、国を尊び、祖先を敬い、国民の生活を安らかで豊かにするものであるべきです。この勉強会は、憲法を学ぶことにより、心を養い、視野を広げ、叡智を身に付け、各々の人生を豊かにすることを理想として行います。
新進気鋭の政治家・学者・経営者必見です。一般の方や学生、初心者の方も大歓迎です。テーマは大きいですが、法律の常識にとらわれない、いつでも質問可、途中入退室自由、少人数のアットホームな場にしようと思います(zoomによる視聴も可能です)
■日時■ 令和2年11月12日(木)午後6時30分~午後8時30分
■場所■ 安達法律事務所 京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木五丁目470番地
竹屋町法曹ビル2階(TEL 075-221-5575)
地下鉄烏丸線丸太町駅 徒歩3分 駐車場なし
■費用■ 1000円(税込) zoom視聴の場合は事前の振込をお願いします。
■定員■ 10名程度(予約順)+ zoom視聴の参加者
■内容■ ほんとうの憲法に関する勉強会 ②憲法の基本原理
弁護士安達悠司の解説により、憲法の基本原理について学びます。第1回は、「憲法と天皇」をテーマに、天皇の存在に基づいて日本思想に基づく憲法の創造的解釈が可能なことをお話ししました。今回は、憲法の基本原理がテーマです。これまで国民主権、人権の尊重、平和主義が三大原理とされてきました。しかし、我が国の法に連続性を認めるとき、わが国の憲法に2000年以上生き続けている基本原理は全く別のものではないかと考えられます。きみ(君)とみ(臣)たみ(民)の関係もその一つです。他には、、、解説90分、質疑応答+意見交換
■申込■ 電話・メール(adachi@adachi-kyoto.com)にてご連絡ください。残席あれば当日参加も可能です。
☆zoom参加の場合☆ 必ず前日までにメールにてご連絡ください。振込先をご連絡しますので、お振込後に配信方法をメールでご連絡します。
≪次回以降の日程(予定)≫
11月18日(水)午後6時30分~午後8時30分 ③十七条憲法
12月 2日(水)午後6時30分~午後8時30分 ④憲法と国防
12月10日(木)午後6時30分~午後8時30分 ⑤これからの憲法とは
(各回は別個の内容であり、単発での参加も可能です。)
4 / 10« 先頭«...23456...10...»最後 »