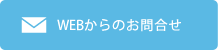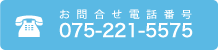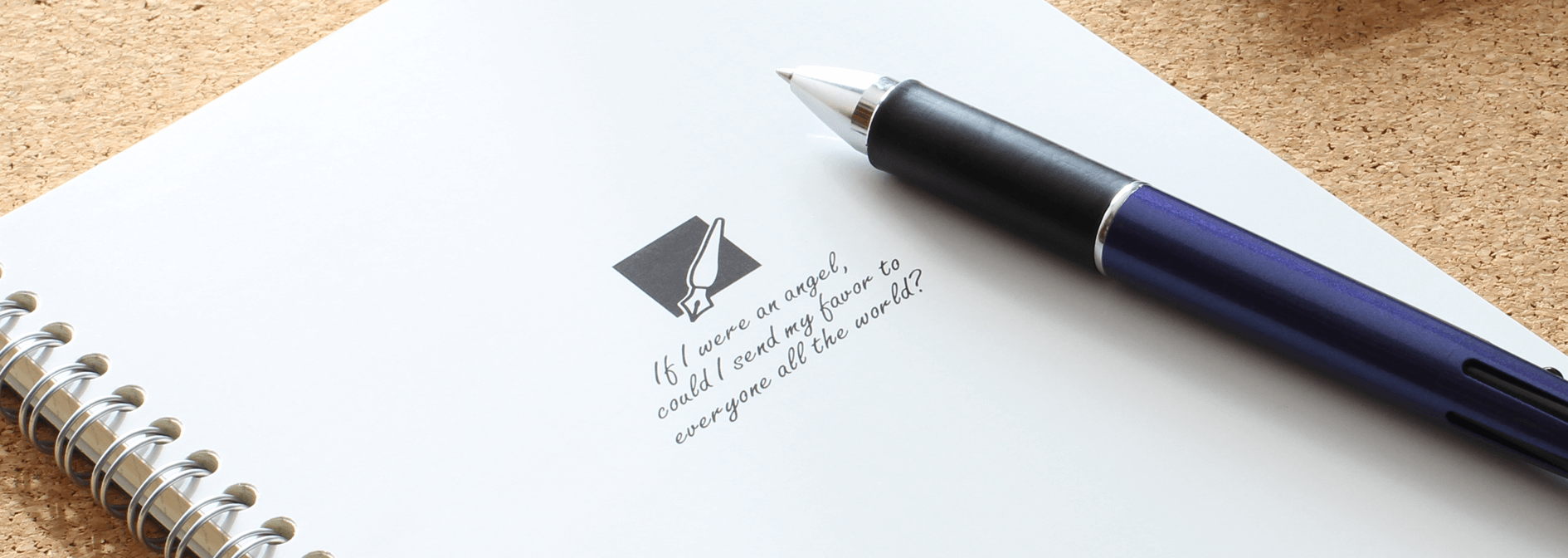11/26(木)弁護士・社労士による勉強会のご案内
11月26日に社会保険労務士さんと勉強会を行います!
テーマは武士道と経営! 以下案内です。
—————————————————————————————————————
日本を元気にする!経営者のための
弁護士・社労士による勉強会のご案内
~武士道を経営に生かす~
弁護士と社会保険労務士による勉強会第5弾です。今回のテーマは「武士道」です。伊邪那岐・伊邪那美二神の「天の沼矛」や須佐之男命の「草薙剣」にも象徴されるように、我が国では太古から「武」は国づくりと共にあり、その道が究められ、日本固有の精神文化を形成してきました。この思想は、経営者にとって学ぶべき日本の叡智の大切な一つです。経営者の方、会社役員の方、会社員の方、団体・法人の方、士業の方、学生の方、初めての方でも大歓迎です。今回も、3密対策を施した上での開催となります。
◆日時◆ 令和2年11月26日(木)午後6時30分~午後8時30分
◆場所◆ ウイングス京都 2階 会議室1
〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 番地
◆内容◆ 武士道を経営に生かす!
1 弁護士・社労士からの発表(90分)
- 「宮本武蔵『五輪書』を読み、経営に生かす」(納谷朋美社会保険労務士(剣道四段))
- 「日本最古の兵法書『闘戦経』に基づく経営戦略」(安達悠司弁護士)
2 参加者からの質疑応答(20分)
◆会費◆ 2000円(会場にて)
◆定員◆ 20名(先着順)
◆申込方法◆
※当日参加も可能ですが、できる限りお早めに申込みをお願いします。
事前にお申込みされる方は、安達法律事務所までご連絡下さい(電話075-221-5575、メールadachi@adachi-kyoto.com)。
十七条の憲法⑨
◆弁護士コラム◆ 十七条の憲法には何が書かれている⑨?
| 信(まこと)は是(こ)れ義(ことわり)の本(もと)なり。事(こと)毎(ごと)に信(まこと)有(あ)れ。其(そ)れ善悪(よしあし)成敗(なりならず)、要(かなら)ず信(まこと)に在(あ)り。群臣(まちきみたち)共(とも)に信(まこと)あるときは、何事(なにごと)か成(な)らざらん。群臣(まちきみたち)信(まこと)なければ、萬事(よろづのこと)悉(ことごと)に敗(やぶ)る。 |
第9条のテーマは「まこと」です。
「信」と書いて「まこと」と読みます。信じるの「信」という字が充てられていますが、例によって訓読みをしますので、「まこと」について書かれているのです。
「誠」「真」「真事」「真言」などの字もすべて「まこと」と読みます。まことは、うそいつわりのないこと、ありのままであること、本当のことを言います。
「義」は「ことはり」または「ことわり」と読みます。「ことわり」はそのとおりであるさま、もっともであること、道理にかなっていることを言います。「断り」「理」も「ことわり」と読みます。
「まこと」は、ありのままであることを言い、それが道理にかなっている「ことわり」となります。
わが国の場合、まことであることは非常に重要視されてきたと考えられます。現在も、日本の法令には、「信義誠実の原則」という規定があります。「信義に従い、誠実にこれを行う」(民法1条2項)、「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」(民事訴訟法2条)、「裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。」(家事事件手続法2条)などと、民事や家事事件の重要な原則とされ、最高裁判所も行政法はじめ様々な事案でも信義誠実の原則、信義則を適用しています。信義誠実の原則は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなるともされています(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。
法律家としてみても、信義誠実の原則は、裁判において意外とよく使われるものです。法律に書かれてはいないが、非常におかしな行動や、不合理なふるまい、前後矛盾する主張などがなされているときに、信義則に反するような行為は許されないと指摘します。そして裁判所も信義則を比較的良く認める傾向にあります。
その信義誠実の原則に使われる、信(まこと)も義(ことわり)もともに十七条の憲法に書かれていることがたいへん興味深く思います。
つまり、裁判の上で、まことであること、道理にかなっていることを、昔も今も、重視してきたのがこの国の思想と言えるのではないでしょうか。
特に、第一文は、まことであることが、もっともなことであり、それがそのまま道理のもとになる、という意味に解釈されます。
儒教では「仁義礼智信」の順に「五常」としておりますが、聖徳太子は、冠位十二階を定めるにあたって、その順位を入れ替え、「徳・仁・礼・信・義・智」としており、「信」を「義」よりも先においています。これらは冠位の名前ですが、あえて訓読みで読むと、「うつくしび」、「めぐみ」、「うやまひ」、「まこと」、「ことわり」、「さとし」となりますので、日本でどのようなものが重要視されてきたかがうかがえるように思います。
要するに、中国では「義」が先の方に来ていますが、日本では「礼」や「信」が義よりも先にあるのです。第4条には「うやまひ」が説かれ、第9条の「まこと」が「ことわり」の本であるとされているのです。こうした発想も、日本ならではの価値観であると考えられます。
つまり、民をいつくしみ、めぐむのが最重要であり、その次にうやまひがあり、そしてまことであることが重視され、そうしたまことが「ことわり」を生み、「さとし」つまり智慧を生むという発想なのです。
このように、民をいつくしみ、めぐむことを重視することや、相手を上に見ること、ありのままであることを重視するのも、言われてみれば当然のこととして、理解することができるのではないでしょうか。
正直であること、嘘をつかないこと、素直であることが美徳とされるのも、日本人の顕著な特徴のように思います。逆に言えば、外国の発想は必ずしもそうではない、ということです。ですから、
十七条の憲法⑧
◆弁護士コラム◆ 十七条の憲法には何が書かれている⑧?
| 八(やつ)に曰く(いは)、群卿百寮(まちきみたちつかさつかさ)、早(はや)く朝(まゐ)り晏(おそ)く退(まか)でよ。公事(おおやけ)鹽靡(いとまな)し、終日(ひめもす)にも尽(つく)し難(がた)し。是(これ)を以(もつ)て遅(おそ)く朝(まゐ)れば、急(すみやか)なるに逮(およ)ばず、早(はや)く退(まか)れば、必(かなら)ず事(こと)尽(つ)きず。 |
第八条は、「勤務時間」がテーマです。
「群卿百寮」は前にもありましたが、「まちきみたちつかさつかさ」つまり、高官から下位の全ての役人に至るまでという意味です。
「朝り」は、「まゐり」と読み、「晏く」は「おそく」、「退でよ」は「まかでよ」、つまり早く参り遅く帰れということを言っています。朝早くから出勤し、遅くに退庁すべしということであり、言わんとするところは明快です。
日本書紀では、舒明天皇8年に、大派王(おほまたのみこ)が豊浦大臣(とよらのおおおみ)に対し、「朝(みかど)参(まゐ)りすること已(すで)に懈(おこ)たれり、群卿(まちきみたち)及び百寮(もものつかさ)、卯の始に参り、巳の後にこれを退れ、因りて鐘を以て節(ととのへ)と為よ」と述べたが、大臣はこれに従わずと書かれています。舒明天皇は聖徳太子が十七条の憲法を制定したときの推古天皇の御代の次の天皇です。十七条の憲法がつくられましたが、その次の天皇の御代には、朝廷に参るのを既に怠っている状況が見られたということです。したがって、卯の始め(午前五時)に参り、巳の後(午前十一時)に退れという具体的な時刻が示され、これを鐘で知らせるように指示されました。しかし、豊浦大臣(蘇我蝦夷)はこれに従わなかったと書かれています。
聖徳太子が十七条憲法を制定したのは推古天皇12年(西暦604年)であり、聖徳太子は推古天皇30年、18年後に亡くなっています。そして、舒明天皇8年(西暦636年)は、実に十七条憲法制定から約32年後です。そのように考えると、全ての役人に実行させるのはいかに困難なことであるかが分かります。
ともかく、当時は、役所で仕事をする時間帯は朝であり、聖徳太子が述べた、早く参り遅く退でよ、という趣旨も、このような早朝の出勤と昼前の退庁を前提としていたと考えられます。
「公事」は、「おおやけ」と読み、「鹽靡し」と書いて「いとまなし」と読みます。おおやけのことは、間隔がないくらいびっちり詰まっているということです。つまり、それだけ仕事の量が多いということです。
第6条の「うたえ」の中でもありましたが、「百姓(おほみたから)の訟(うたえ)は一日(ひとひ)に千事(ちわざ)あり」とされていました。それだけ公務の量も多く、多忙だった姿がうかがえます。
「終日」は「ひめもす」あるいは「ひねもす」と読み、もとは太陽が昇っている間中という意味ですが、転じて一日中という意味です。
したがって、遅く参ると、「急なるに逮ばず」。「逮ばず」は「およばず」と読み、速やかな案件が出てきたときに対応することができないということになります。早く退庁すれば、必ず仕事が終わらないということです。
この条の訳を以下にまとめます。
「第八条 すべての役人は朝早く出勤し(朝)遅くに退庁しましょう。公のことは休む間もなく、一日中働いても終えることができません。したがって遅くに出勤すれば、急な事案に対応することができず、早く退庁すれば必ず仕事が終わりません。」
以上
十七条の憲法⑦
◆弁護士コラム◆ 十七条の憲法には何が書かれている⑦?
| 七(ななつ)に曰(いは)く、人(ひと)各(おのおの)任(よさし)有(あ)り、掌(つかさど)ること宜(よろ)しく濫(みだ)れざるべし。其(そ)れ賢哲(さかしきひと)官(つかさ)に任(よさ)すときは、頌音(ほむるこゑ)則(すなは)ち起(おこ)り、姧者(かたましきひと)官(つかさ)を有(たも)つときは、禍(わざはひ)乱(みだれ)則(すなは)ち繁(しげ)し。世(よ)に生(う)まれながら知(し)ること少(すく)なけれども、剋(よ)く念(おも)ひて聖(ひじり)と作(な)る。事(こと)大少(おほひなりいささけき)となく、人(ひと)を得(え)て必(かなら)ず治(おさ)まる。時(とき)急緩(ときおそき)となく、賢(さかしきひと)に遇(あ)ひて自(おのづか)ら寛(ゆたか)なり。此(これ)に因(よ)りて国家(あめのした)永(なが)く久(ひさ)しくして、社稷(くに)危(あやう)きこと勿(な)し。故(か)れ古(いにしへ)の聖(ひじりの)王(きみ)、官(つかさ)の為(た)めに以(もつ)て人(ひと)を求(もと)む、人(ひと)の為(た)めに官(つかさ)を求(もと)めたまはず。 |
第七条は、「任官」がテーマです。
第一条から振り返ってみると、第一条は「やはらぎ」、第二条は「仏教」、第三条は「つつしみ」、第四条は「うやまひ」、第五条は「うたえ」、第六条は「善悪」でした。
第一条は、上司がなごやかな空気を作り出すことで心を一つにすることを説き、第二条は心を平穏にするための教えとして仏教を説き、また第三条では天皇陛下のお言葉を受けたときに我が身を振り返ってよく考えることを説いています。そして、第四条では具体的な行動として、相手を上に見る行動をすることで互いに尊重しあう世の中にし、第五条では訴えを公平に審理することで民の拠り所をつくり、第六条では人の良い行動をたたえ、悪い行動を戒めるという行動実線を説きました。
十七条の憲法は、既に述べたように冠位を持つ者への教え、行動哲学として述べられたものであり、非常に実践的な内容です。同時に、国をいかにして治めるか、いかにして民を豊かに安らかにするかという思いが根本にあります。そして、我が国古来の思想や法律、教えをベースにしながら、仏教の考え方や中国の思想・表現を取り入れていることが分かります。
そして、よく読めば、印度と中国の思想を単に取り入れたものではなく、あくまで日本の古来の思想や教えに基づきながら、印度や中国にはない、新たな教えを作り出しているのが本当のところだと感じられます。その例が、第一条の「やわらぎ」や第三条の「つつしみ」であり、また、第四条の「うやまひ」を庶民にまで広げるなど、我が国固有の思想や発想だと分かります。また、第六条や第十六条では、「古の良き典(のり)なり」として我が国の古くからの法律・しきたりを指摘しています。
第七条でも最後に、「古の聖王は」とありますが、これは「いにしえのひじりのきみ」と読み、我が国のおおきみのことを指します。たとえば、日本書紀には、第11代の垂仁天皇の御代、朝鮮半島にあった加羅国の王子が「日本国(やまとのくに)に聖皇(ひじりのきみ)有すと聞りて帰化す」と書かれています。「王」も「皇」も「きみ」と読みます。加羅国の王子が、日本に「ひじりのきみ」がいらっしゃると承って帰化したのです。ほかにも新羅国王の子が「日本国(やまとのくに)に聖皇(ひじりのきみ)有すと聞り」と来日したことが書かれてあります。
したがって、第七条も、日本古来の教えをもとに、任官の考え方を説いているのです。
まず「任」は「よさし」と読みます。任せることを「よさす」と言いました。「よさす」は「寄さす」意味と考えられます。祝詞に詳しい方がいらっしゃれば、神社の大祓詞でも、二神が皇孫に対し、日本を治めることを「ことよさしまつる」(お任せになった)という下りがあります。
人各任有りとは、人はそれぞれ任せられた務めがあるという意味です。
「濫れざるべし」は濫り(みだり)に行ってはならないという意味であり、任務を適切に行わなければならないということです。
第七条の最後に、「官のために人を求め、人のために官を求めず」とありますが、本条の趣旨はまさにこのとおりで、任務を適切に行うことができる人を求めなければならないということです。
「賢哲」は「さかしきひと」つまり優秀な人という意味です。「頌音」は「ほむるこゑ」つまり優秀な人を任官させると褒め称える声が聞こえるということです。
第2文までを訳します。
人にはそれぞれ任された務めがあり、その務めを適切に行わなければなりません。賢い人を任官させると、褒め称える声が起こり、悪い人が官にあり続けると災いや乱れが多くなります。
また、世に生まれながら知る人は少ないけれども、よく考え学んで「ひじり」となる。「聖」は「ひじり」と読みますが、「ひじり」は「日+知り」からきていると思われ、日に日に知ることで、ひじり(聖)となるわけです。「大少」は「おほいなりいささけき」と読みますが、大きいこともわずかなこともという意味です。
「急緩」は「ときおそき」と読みますが、緊急のときでもという意味で、「寛」は「ゆたか」と読み、ゆるやかという意味です。「社稷」は音読みすると「しゃしょく」ですが「くに」(国)のことです。
第6文までを訳します。
世に生まれながら知ることは少ないけれども、日に日によく考え学ぶことで立派な人、ひじりとなります。重大なことでも些細なことでも、よい人がいれば必ずうまくゆきます。急を要することでも、賢い人がいると自然と落ち着いて対処することができます。こうすれば、国は長きにわたって危ういことがありません。
「古の聖王」は、前段でも述べましたが、「いにしへのひじりのきみ」と読み、我が国の昔の優れた大王(おおきみ)・天皇(すめらみこと)のことです。
最後の文を訳します。
よって我が国昔の優れた大王(おおきみ)は、官職のために人を求め、人のために官職を求めませんでした。
まとめると、次のようになります。
「第七条 人にはそれぞれ任された務めがあり、その務めを適切に行わなければなりません。賢い人を任官させると、褒め称える声が起こり、悪い人が官にあり続けると災いや乱れが多くなります。世に生まれながら知ることは少ないけれども、日に日によく考え学ぶことで立派な人、ひじりとなります。重大なことでも些細なことでも、よい人がいれば必ずうまくゆきます。急を要することでも、賢い人がいると自然と落ち着いて対処することができます。こうすれば、国は長きにわたって危ういことがありません。よって我が国昔の優れた大王(おおきみ)は、官職のために人を求め、人のために官職を求めませんでした。」
結局、第七条では、任官の際には、その務めを行うのにふさわしい優れた人を求めるよう説いています。これは、当たり前と言えば当たり前のことですが、官職にある者の血縁や地縁ということでの任官、つまり縁故採用が多くなった結果、その任に堪えない者がでてくる弊害が起きていたためと考えるのが自然です。
人は第一の宝です。どんな優れた制度やどんな役職をつくっても、それを動かすのは結局人ですから、よい人が就けばうまくゆきますし、その任に堪えない人が就けばうまくゆきません。聖徳太子はまさにこのことを言っています。
以上
十七条の憲法⑥
◆弁護士コラム◆ 十七条の憲法には何が書かれている⑥?
| 六(むつ)に曰(いは)く、悪(あしき)を懲(こら)し善(よき)を勧(すす)むるは古(いにしへ)の良(よ)き典(のり)なり。是(これ)を以(もつ)て、人(ひと)の善(よき)を匿(かく)すこと無(な)く、悪(あしき)を見(み)ては必(かなら)ず匡(ただ)せ。其(そ)れ諂(へつら)ひ詐(あざむ)く者(もの)は、則(すなは)ち国家(あめのした)を覆(くつがへ)す利器(ときうつわ)たり、人民(おほみたから)を絶(た)つ鋒(とき)剣(つるぎ)たり。亦(また)侫(かたま)しく媚(こ)ぶる者(もの)は、上(かみ)に対(むか)ひては則(すなは)ち好(この)みて下(しも)の過(あやまち)を説(と)き、下(しも)に遭(あ)ひては則(すなは)ち上(かみ)の失(あやまち)を誹(そ)謗(し)る。其(そ)れ如(これ)此(ら)の人(ひと)は、皆(みな)君(きみ)に忠(まめ)無(な)く、民(たみ)に仁(めぐみ)無(な)し。是(こ)れ大乱(おほきなるみだれ)の本(もと)なり。 |
第六条は「善悪」がテーマです。
「勧善懲悪」を前後逆にした「懲悪勧善」という四字熟語が最初に出てきます。
つまり、悪を懲らし善を勧める、悪いことを懲らしめ良いことを称えるという道徳の基本的なことが説かれています。
「懲悪勧善」は、中国の古典の「春秋」という書物にも書かれており、聖徳太子がこの記載をもとに引用した可能性が高いと言われています。
ただ、「古の良き典なり」とも書かれています。つまり、昔の良い「のり」である、ということです。
「典」は「のり」と読み、のりは、神が述べたことから転じて、「ことば」「きまり」「しきたり」「おしえ」などという意味があります。宣、法、則、範、教という字はいずれも「のり」と読みますが、「のり」にはこのように様々な意味があるのです。
ここで、懲悪勧善が昔からの良い「のり」であるとなると、わが国に昔からある法律・しきたり・教えという意味に解釈されるのではないかと思います。
そうすると、悪いことをこらしめ、良いことを称えることは、わが国でも昔から教えられ、きまりやしきたりとなっていた、と解釈するのが自然に思います。
中国の古典に書かれている言い回しは、わが国に古くからある道徳を漢文に翻訳したときに、同じような意味にあるものとして使われたのではないでしょうか。
むしろ、ここで強調されているのは、第2文の「人の善を隠さず、悪を見ては必ずただせ」という、具体的な行動です。人の良い行動を見たら隠さない。つまり、上司に報告しなさいということです。また、人の悪い行動を見たら正す。つまり、その場で注意しなさいということです。これは、言うのは簡単ですが、行うのは難しいこともあります。
そして、へつらい、あざむく者は、国家を覆す「利器」とされます。へつらいあざむくとは、悪いことに従い、嘘をついて人をだますことを言います。「利器」は「ときうつわ」と読み、鋭い道具ということです。また、人民を絶つ鋒剣、つまり「鋒剣」は「ときつるぎ」と読み、鋭い剣のことです。非常に強い言い方がされています。
第3文までを訳します。
悪いことを懲らしめ、良いことを称えるのは、わが国に昔からある良いしきたりです。したがって、他人の良い行動を見つけたら隠さず報告し、悪い行動を見つけたら必ず正しましょう。悪いことを正さず、見て見ぬふりをしたり、悪いことに従うような、へつらいあざむく人は、(悪事がはびこる原因となるため)国をくつがえすのに便利な道具であり、(国がくつがえると民は路頭に迷いますから)民を切る鋭い剣のようなものです。
また、「侫しく媚ぶる」は「かたましくこぶる」と読み、言葉巧みに相手に追従する人を言います。上司に対しては部下のミスを喜んで話し、部下に会ったら上司のミスを非難するような人が挙げられています。
これは、「へつらいあざむく者」が悪を正さずに悪に従ってしまう人を指しているのに対し、「かたましくこぶる者」は悪事を指摘してばかりで、人の善を称えることをしないことを指すと考えられます。
こうした人は「皆君に忠なく、民に仁なし」とされます。
ここで、「忠」は「まめ」と読み、「仁」は「めぐみ」と読みます。
言葉巧みに相手に追従し、他人の悪いことばかり指摘して、他人の良い行動を称えない人は、模範となるべき行動を見て見ぬふりをするので、良い人を称賛する機会を失わせてしまいます。これでは、「君」すなわち天皇に忠節を尽くしておらず、民を良い方向に教えさとすことが役人の仕事であるのに、それをしていないのですから、民を恵むことができません。これは、国を乱れさせる原因になっていまいます。
後半を訳します。
また、言葉巧みに追従する人は、上司に対しては好んで部下の誤りを話し、部下に会ったときは上司の誤りを非難します。これらの人は、他人の悪い行動を指摘するばかりで、他人の良い行動を話したり、称えることをせず隠しているので、皆天皇に忠実でなく、また、(民を良い方向に教え諭すという仕事をしていないので)民に恵むことがありません。これは、大いなる乱れの原因になります。
まとめると、次のようになります。
「第六条 悪いことを懲らしめ、良いことを称えるのは、わが国に昔からある良いしきたりです。したがって、他人の良い行動を見つけたら隠さず報告し、悪い行動を見つけたら必ず正しましょう。悪いことを正さず、見て見ぬふりをしたり、悪いことに従うようなへつらいあざむく人は、(悪事がはびこる原因となるため)国をくつがえすのに便利な道具であり、(国がくつがえると民は路頭に迷いますから)民を切る鋭い剣のようなものです。また、言葉巧みに追従する人は、上司に対しては好んで部下の誤りを話し、部下に会ったときは上司の誤りを非難します。これらの人は、他人の悪い行動を指摘するばかりで、他人の良い行動を話したり、称えることをせず隠しているので、皆天皇に忠実でなく、また、(民を良い方向に教え諭すという仕事をしていないので)民に恵むことがありません。これは、大いなる乱れの原因になります。」
このように、役人が、悪い行動を見て見ぬふりをしたり、悪いことに従うのは非常に危険です。また、良い行動を見て見ぬふりをして称えず、人の悪いことばかりを指摘するのも、結局は嘘をついているのと同じであり、正しい情報が行き渡らず、国を大きく乱れさせる原因となるのです。
当たり前のことが説かれているようですが、いざ実践となると、大変なことです。しかしながら、良いことを良いとして賞賛し、悪いことを悪いこととして正すのは、わが国古来からの当然のしきたりだったわけです。聖徳太子は、こうした、古来からの在り方に立ち返って、初心忘るべからず、もう一度行動してみましょう、と諭しているのです。
以上
5 / 10« 先頭«...34567...10...»最後 »